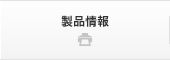- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
作品をギャラリーで発表したい人、写真集をつくりたい人、ミュージアムピース(美術館に収蔵される作品)を目指す人など、写真に真剣な皆さんに向けて、北島敬三さんがご自身の意見を語ってくれました。前編として今回は“なぜプリントにこだわるべきなのか”を考えます。
写真が絵画などと同じように“ファインアート(芸術作品、美術品)”として扱われるようになったのは、意外にもごく最近の話です。海外では、60年代にはすでに美術の文脈で写真が認められていましたが、日本ではもう少し後になります。70年代半ば頃からオリジナルプリントを展示・販売するギャラリーができ始め、写真部門をもつ公立の美術館、例えば東京都写真美術館や川崎市市民ミュージアムなどができたのは、80年代の後半から。わずか20~30年前です。まだ歴史が短いだけに、写真をめぐる状況は日々刻々と変化しています。
最近では、美術館が収蔵する写真の中に、銀塩プリントだけでなくインクジェットプリントが見られます。東京都写真美術館でもそうですが、ロンドンのテート・モダン、ニューヨーク近代美術館(MoMA)でも同じです。また、アートのコレクターたちが集う有名なオークションで、インクジェットプリントの写真に驚くような高値が付いて話題になりました。ですから「インクジェットプリントは認められるか」といった議論はもはや意味がありません。
材料が少なくなり銀塩の手法が難しくなりつつある以上、インクジェットプリントが作品のメディウム(制作材料)として浸透していくのは自然なことですし、相応のクオリティを実現しています。
同じように「デジタルタイプCプリント」と呼ばれる、アナログ印画紙とレーザー露光機を使った方式も選択肢となっています。ただデジタルタイプCだと、プリントしてから色を確認できるまでに時間がかかることと、現像液の管理が難しいということがあり、私はインクジェットプリンター「PX-9550」を主に使っています。インクジェットならプリントから1時間後には色が落ち着いて、永続的な結果を確認できる。これが非常にありがたいですね。

■ この秋、八戸市美術館にて開かれた「北島敬三 種差 scenery」展の様子。展示された50点のプリントはすべて、北島氏が自らインクジェットで制作した。
さきほどお話ししたような、美術館や企業や一部のアートコレクターによって収集される写真は非常に高い金額で売買され、普通の人には関係のないところで完結します。ですが、写真のマーケットはそれだけではありません。
今は、エプサイトのようないわゆるメーカーギャラリーのほかに、企業が関わらない独立系フォトギャラリーがたくさんあります。それらは、ギャラリストが作家を集めて企画・運営しているところ、作品を発表したい人が自ら場をつくったところ、発表者を募るかたちのところなど、形態も規模もさまざまです。また「パリ・フォト」「東京フォト」など、写真だけのフェアも多数開かれ、活発に写真がやりとりされています。こうしたギャラリーやフェアでは、普通の人にも手が届くところに写真があります。またプリントという形態だけでなく、写真集やzine(ジン)(手製の少部数の冊子)も人気で、専門の書店やフェアがあります。つまり写真を発表する場所も機会も方法も増えているし、そのためのツールはすぐに手に入るのです。

■ photographers'gallery(東京・新宿)。複数の作家が共同運営し、北島氏もメンバーの一人。
どんな形態を選ぶにしても、発表する、売買する、収集するといったすべてのシーンにおいて、写真は「物」として存在しています。「写真はイメージだ」とよく言われますが、作家の頭の中を取り出して見せることはできないので、提示するときは現実に存在する「物」にしなくてはいけない。言い換えるなら、購入されたり収蔵されるのは「プリント(または本)」だ、ということ。だから物質と関わる部分をおろそかにしてはいけません。インク、紙、サイズ、展示方法を決めるというのは、すべて物質と関わることです。
そして、誰にとってもいいプリント、というのは存在しません。その作品にとっていいプリントは1種類であり、作家本人が追求するしかない。だから私はプリントで妥協している作品を見ると、サボタージュだと思ってしまう。
自分の理想のプリントを求める作業とは、ある仮説を立て、それに向かってやってみる、という作業の繰り返しです。最初から明確なゴールが見えているわけではありません。試行錯誤の末に探し当てたものこそが、自分の今やっている作品にとって“これしかないもの”になるのです。


■ 「種差 scenery」シリーズより。「用紙をプレミアムマット紙から半光沢のプロフェッショナルフォトペーパー〈厚手半光沢〉に変えたところ、黒が締まって、ちょっとインパクトを出したいと思っていた部分にうまく効いた」と北島氏。
そのためには、手を動かすことです。思いついたことは全部やってみるといい。プリントすれば答えはすぐにわかるのですから。それが、作家にとって頭を使うということにほかなりません。
それに写真というメディアは、常にテクノロジーの発展とともにある。こんな機器が生まれたからこんな表現が生まれた、ということの繰り返しです。だから作家は新しい技術・技法を取り込むことに貪欲にならざるをえない。今なら、インクジェットプリンターを使いこなすことも必要になってくる。
同時に、いいプリントを見る経験も大事です。どんどん美術館やギャラリーに行って、プリントを見てみるといい。誰でもプリントできる今だからこそ、上質なものに触れることが、より重要である気がします。
さて、プリントがうまく出来たとしても、それを発表するためには、第三者にプレゼンしなくてはいけません。その際に大事なのは、ギャラリーに展示したいのか写真集にしたいのかといった“自分の目的”に応じたプレゼンテーションをすることです。描いているゴールによって、写真の見せ方は変わります。後編では、そんなお話しをしたいと思います。
 |
北島敬三 Keizo Kitajima 1954年、長野県生まれ。WORKSHOP寫真学校の森山大道教室に参加。 1976年よりイメージショップCAMPに参加。独自の作品発表方法で注目される。 1983年『NEW YORK』で木村伊兵衛写真賞を受賞。 他の作品集に『USSR 1991』『A.D.1991』などがある。 |
|---|